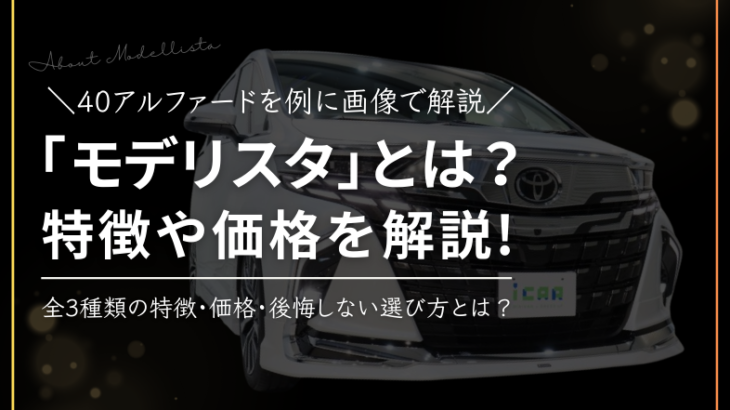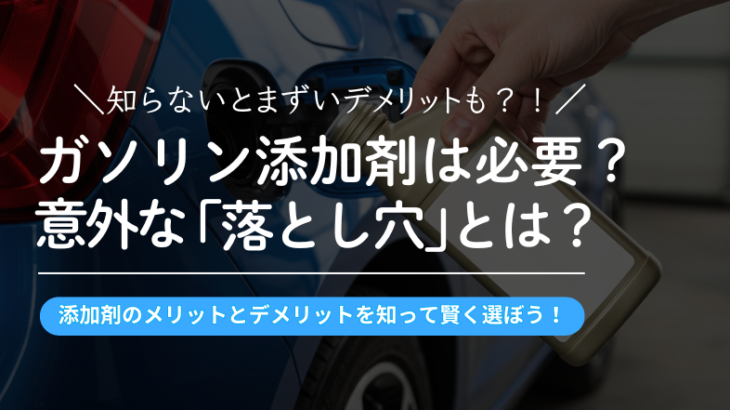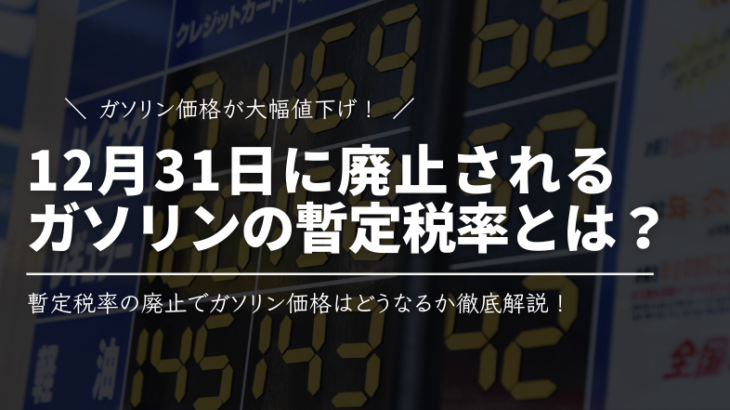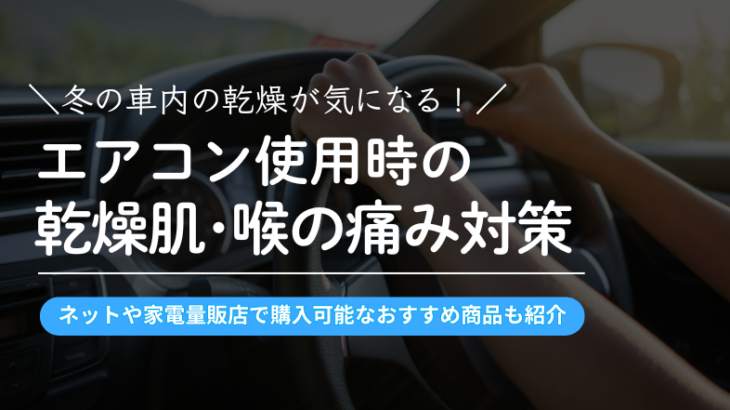こんにちは!アイカーマガジン編集部です!
2025年4月から、車検制度が大きく変わったことをご存じでしょうか?
今回の改正は、車をお持ちのすべての方に関係する、とても大切な内容です。
この記事では、最新の変更点、どんな車が対象なのか、どのようなメリットや注意点があるのかを、わかりやすくご紹介します。
\YouTubeもよろしくお願いします✨/
車検制度改正の背景

車検制度は1951年のスタート以来、時代の変化やクルマの進化に合わせて何度も見直されてきました。
最近では自動車の保有台数が増え、年度末や大型連休前などに車検が集中しがちになっています。
そのため、整備工場やディーラーで予約が取りづらくなったり、希望日に車検を受けられなかったり、整備士さんの長時間労働が問題になることもありました。
また、デジタル化の進展により、車検証や自賠責保険証明書の電子化、キャッシュレス決済の普及など新しい流れも生まれています。
こうした背景から「もっと柔軟で効率的な車検制度への見直し」が求められてきたのです。
2025年4月改正の主な内容
ここでは2025年4月から改正された車検の内容についてご紹介します。
1. 受検可能期間の拡大
今回の改正で特に注目されるのは、車検(継続検査)を受けられる期間が「満了日の1カ月前」から「2カ月前」へと広がったことです。
たとえば、車検満了日が6月15日の場合、これまでは5月15日からしか受検できませんでしたが、改正後は4月15日から受けられるようになりました。
この変更によって、年度末(特に3月)や繁忙期の混雑を避け、余裕を持ったスケジュールで車検を受けることができます。
また、早めに車検を受けても次回の車検満了日は従来通り「満了日から2年後(新車は3年後)」のままです。
早く受けても有効期間が短くなることはありません。
仕事や家庭の都合で日程調整が難しい方にも、より柔軟に車検を受けられるようになりました。
なお、離島の特例車両を除き、ほとんどすべての自動車(自家用乗用車・軽自動車・貨物車・大型特殊自動車など)が対象となります。
日本国内で公道を走る車なら基本的にこの制度が適用されます。
2. 自賠責保険の更新期間も拡大
自賠責保険も、車検と同じく「満了日の2カ月前」から更新できるようになりました。
車検と保険の手続きを同時に早めに済ませられるので、保険切れのリスクも抑えられます。
特に、年度末などの混雑期には、手続きの分散による利便性アップが期待されています。
3. 仮ナンバー利用の頻度減少
受検期間が広がったことで、車検切れによる仮ナンバー(臨時運行許可番号標)の発行が必要になる可能性が大幅に減りました。
これまでは混雑や手続きの遅れで車検が切れてしまい、仮ナンバーを使わざるを得ないこともありましたが、今後は余裕を持って車検を受けられるので、手間やコストの削減にもつながります。
4. OBD検査の本格導入
2024年10月からは車の電子制御システムに異常がないかを専用機器で診断する「OBD検査(車載式故障診断装置による検査)」が本格的に導入されています。
「OBD検査」は2021年10月以降に新型車として発売された国産車や、2022年10月以降の新型輸入車が対象です。
従来の目視中心の検査に加え、電子的な不具合も早期発見できるようになり、安全性や環境性能の向上が期待されています。
車検時に必要な書類と手続きの流れは?

車検を受けるときに必要な書類、意外とたくさんあって戸惑う方も多いですよね。
主に必要なものは次の通りです。
- 自動車検査証(車検証)
- 自賠責保険証明書
- 自動車税(または軽自動車税)納税証明書
- 本人確認書類(運転免許証など)
もし代理の方が手続きをする場合は、委任状も必要となります。
なお、ユーザー車検を選ぶ場合は、さらに自動車検査票や自動車重量税納付書、継続検査申請書、定期点検整備記録簿も必要です。
書類に不備があると手続きが進まないため、事前にすべて揃っているか確認しておきましょう。
\ユーザー車検については以下をご覧ください/
必要書類を紛失しないために
車検証や納税証明書は、普段あまり使わないため紛失しやすい書類です。
日ごろから車のダッシュボードや自宅の決まった場所にまとめて保管しておき、車検のタイミングで慌てないようにしましょう。
電子車検証の場合も、スマートフォンやパソコンで確認できるようにしておくと安心です。
制度改正による主なメリット

先述した通り、今回の改正でいちばん大きなポイントは、車検を受けられる期間が「満了日の1カ月前」から「2カ月前」へと広がったことです。
手続きの変更だけでなく、車を利用する皆様や整備業界にとってもたくさんのメリットがありますので具体的なメリットをご紹介します。
1. 車検予約の選択肢が増える
受検期間が2カ月間に広がったことで、ご自身のライフスタイルやお仕事の都合に合わせて、より柔軟に車検日を選べるようになりました。
これまで混雑しがちだった年度末や大型連休前も避けやすくなり、計画的に車検を受けられるのは大きな魅力です。特に、平日は忙しい方や家族の予定に合わせたい方にはうれしいポイントとなるでしょう。
2. 混雑緩和と整備士の負担軽減
車検が一時期に集中しなくなったことで、整備工場やディーラーの混雑もかなり緩和されました。
その結果、整備士やスタッフの負担も分散され、サービスの質が上がったり、より丁寧な対応をしてもらいやすくなっています。
待ち時間が短くなるのもうれしいですね。
3. 車検切れリスクの低減
以前は予約が取れず、うっかり車検満了日を過ぎてしまうリスクもありましたが、受検期間が広がったことで、余裕を持ってスケジュールを立てやすくなりました。
車検切れによるペナルティや仮ナンバー発行の手間・費用も大幅に減っています。急な予定変更があっても安心です。
4. 計画的な整備・修理がしやすい
車検の受検期間が長くなったことで、もし修理や部品交換が必要になっても、焦らず余裕を持って整備が進められるようになりました。
急なトラブルや追加費用の発生も抑えやすくなり、計画的なカーライフを送りやすくなっています。
5. デジタル化・キャッシュレス化でさらに便利に
電子車検証やキャッシュレス決済が広がり、手続きもどんどんスムーズになっています。
スマートフォンで進捗を確認したり、アラート通知を受け取ったり、オンラインで予約できるなど、デジタル技術を活用した便利なサービスも増えています。
6. 安全面においてもプラスになっている
OBD検査の本格導入で、車の電子制御システムに異常がないかしっかりチェックできるようになりました。
これまで目視では見逃されがちだった電子的な不具合も早めに発見できるため、交通安全や環境保全にも大きく役立っています。
| メリット | ポイント・内容 |
|---|---|
| 車検予約の選択肢が増える | 2カ月前から予約可能。混雑期を避けて柔軟に日程調整できる。 |
| 混雑緩和と整備士の負担軽減 | 工場やディーラーの混雑減。サービス向上・待ち時間短縮。 |
| 車検切れリスクの低減 | 余裕を持った受検で車検切れや仮ナンバーの手間が減少。 |
| 計画的な整備・修理がしやすい | 修理や部品交換も余裕を持って対応可能。 |
| デジタル化・キャッシュレス化 | 電子車検証やキャッシュレスで手続きが簡単・便利に。 |
| 安全面・環境面での向上 | OBD検査導入で不具合を早期発見、交通安全や環境保全にも貢献。 |
注意点とデメリットはどう?

制度改正にはたくさんのメリットがありますが、気をつけたいポイントや注意点もいくつかあります。ここでは、特に知っておきたい点をまとめました。
1. 早めに受けても満了日は変わらない
車検を2カ月前から受けても、次回の車検満了日は今まで通り「前回満了日から2年後(新車は3年後)」です。
早めに受検しても有効期間が短くなることはありませんが、「せっかく早く受けたのに損した」と感じる方もなかにはいるかもしれません。
制度の仕組みをきちんと理解し、計画的に受検しましょう。
2. 制度変更を知らないと損をする?
仮に制度変更を知らず、今まで通り直前に予約を取ると混雑や車検切れのリスクが残ったままです。
また、OBD検査や電子車検証など新しい制度に未対応の整備工場を選んだ場合、追加費用や手間がかかることもあります。
3. 特殊車両や構造変更車両は?
A. 継続検査(通常の車検)のみが対象です。構造変更(車体寸法や定員変更など)がある場合や、不正改造車は別途検査や手続きが必要です。
また、車検切れ車両や特殊用途車両など一部の場合では異なるルールが適用されます。
4. デジタル化への対応
電子車検証やキャッシュレス決済などデジタル化が進む一方で、スマートフォンやパソコンの操作に慣れていない方には、手続きが難しく感じられる場面もあるかもしれません。
今後はサポート体制の充実や、窓口での丁寧な案内もますます大切になってきます。
| 注意点・デメリット | 内容・ポイント |
|---|---|
| 早めに受けても満了日は変わらない | 2カ月前に受けても満了日は変わらず、有効期間は短縮されない。 |
| 制度変更を知らないと損をする可能性 | 直前予約だと混雑・車検切れリスク。新制度未対応工場では手間や追加費用も。 |
| 特殊車両や構造変更車両は対象外 | 継続検査のみ対象。構造変更車や特殊車両は別途手続きが必要。 |
| デジタル化への対応 | デジタル手続きが苦手な方には難しい場合も。今後はサポート充実が重要。 |
よくある質問
Q. 自賠責保険の更新方法は?
A. 自賠責保険の更新は、ほとんどの場合、車検と一緒に手続きします。多くの方は業者に依頼するので、必要な書類をそろえておけば、あとはお任せで大丈夫です。
ご自身でユーザー車検を受ける場合は、運輸支局や保険会社の窓口で手続きをすることになりますが、事前に準備しておけばスムーズに進みます。
Q. 改正が適用されないケースはある?
A. 継続検査(通常の車検)のみが対象です。
構造変更や不正改造車、車検切れ車両、特殊用途車両などは別途手続きや検査が必要となります。
Q.どの日に車検を受けるのが一番お得?
A. 今回の改正後、一番得する車検日は満了日の2カ月前ぴったりの日です。
例えば、車検満了日が6月15日の場合、4月15日が最もお得な日となります。満了日の2カ月前当日に車検を受けることで、車検の有効期間を最大限に活用でき、損をすることはありません。
Q. 法改正の社会的意義は?
A.今回の改正は、整備士の方の働き方をより良くしたり、私たちが安心してクルマを使える社会づくりにつながっています。
電子車検証やOBD検査が広がることで、これから進む自動運転やネットにつながる車の時代にも、しっかり対応できる土台ができていく大切な一歩です。
制度改正を上手に活用するためのポイントは?
- 車検の満了日をあらかじめチェックして、2カ月前からの予約をうまく活用しましょう。
- 必要な書類や手続きの内容は早めに確認し、紛失や不備がないように整理しておくと安心です。
- OBD検査や電子車検証など、新しい制度や技術に対応している整備工場を選ぶのもおすすめです。
- オンライン予約や進捗確認など、便利なデジタルサービスも積極的に利用してみましょう。
- 車のメンテナンス履歴や点検記録をデジタルで管理しておくと、万が一のトラブル時にもスムーズに対応できます。
まとめ
2025年4月の車検制度改正は、受検期間が広がったことやデジタル化の進展、OBD検査の導入など、ユーザーの皆さんにも整備業界にもたくさんのメリットをもたらしています。
制度のポイントをしっかり押さえて、早めの車検予約や計画的なメンテナンスを心がけることで、車検切れや手続きのトラブルもぐっと減らせます。
この記事が、2025年4月からの車検制度改正をより身近に感じていただき、日々のカーライフや手続きに少しでもお役立ていただけたら幸いです。