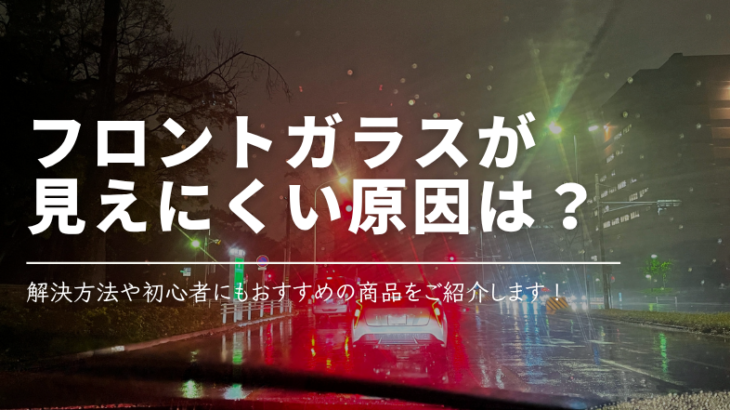こんにちは!アイカーマガジン編集部です!
車を運転していると「音楽(やラジオなど)を聴きたい」「電話をしながら移動したい」と、イヤホンを使う人は多いかもしれません。
しかし、「イヤホンをつけて運転すると違反になる」と聞いたことはありませんか?実際に道路交通法や都道府県の決まりでは、この点についてどのように定められているのでしょうか。
本記事では、イヤホンをつけた運転がなぜNGとされるのか、その根拠や違反となるケース、罰則について分かりやすく解説します。
イヤホンをつけて運転すると違反になる?

はじめに押さえておきたいのが「交通ルール上、イヤホンは禁止されているのか?」という点です。
結論からいうと、道路交通法の条文に「イヤホン禁止」と明記されているわけではありません。
しかしイヤホンの使用によって周囲の音が聞こえにくくなり、状況を十分に判断できなくなったり、事故を起こした場合には「安全運転の義務」(道路交通法第70条)に違反したと判断され、違反点数や罰金など、処罰の対象になる可能性があります。
安全運転義務とは?
道路交通法第70条では、ドライバーに以下の義務が定められています。
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
つまり「運転に支障をきたす行為をしないこと」が前提です。
イヤホンのせいで周囲の音が聞き取れず、状況判断に影響が出れば違反とされるのです。

イヤホン運転が危険とされる理由
イヤホンを装着しながらの運転は、「周りがやっているから大丈夫」「片耳なら聞こえるから平気」と思っていませんか?
イヤホンを運転中に装着する行為が問題視されるのは理由があります。
1.大切な音が聞こえなくなる

イヤホンをつけて運転すると、「踏切音やサイレン、クラクション、自転車のベル」など、事故を防ぐために大切な音が聞き取りにくくなります。
その結果、周囲の状況把握が甘くなり、重大事故を避けるための対応が遅れてしまったり、そもそも気づかずに事故になるリスクが高まります。
特に両耳イヤホンを使用していると、ほぼ外音が遮断され、緊急の状況を把握できなくなります。
2.方向感覚が鈍る
例えば両耳で音の方向を感じ取ったり、「サイレンが左後方から近づいている」と分かるのは、耳で方向感覚を補っているからです。
しかし、イヤホンをつけて運転すると音の方向が分かりにくくなり、車や人がどこから近づいているかを正確に感じ取りにくくなります。
3.注意力が散漫になる
上記に加えて、音楽や通話に集中してしまうと運転への注意が散漫になり、運転がおろそかになります。
電話に集中すると「ながら運転」状態になり、前方不注意が増えてしまいます。
「片耳イヤホン」「小音量」でも大丈夫?
よくある誤解が「片耳だけ」「音量を小さめにすれば違反にならない」という考え方です。
実際には、片耳イヤホンでも周囲の音を十分に聞き取れなければNGです。また「音が小さいから安心」と思っても、注意力が音楽や会話に向いてしまう点は変わらず、事故リスクは消えません。
さらに、ノイズキャンセリングや密閉型イヤホンは小音量でも外部音を大幅に遮断します。結果的に両耳イヤホンと同等に危険となる可能性があります。
つまり、「片耳だから大丈夫」とは言い切れないのです。
イヤホン運転の罰則とは?
「じゃあもし違反とみなされたらどうなるの?」―気になるのは処罰や罰則の内容でしょう。
ここでは違反点数などの罰則内容についてご紹介します。
道路交通法・安全運転義務違反の場合
1.違反点数:2点
2.反則金
- 普通車:9,000円
- 大型車:12,000円
- 二輪車:7,000円
- 原付:6,000円
場合によっては、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金もあり得ます。
都道府県条例違反の場合
条例違反の場合、道路交通法違反と違い違反点数の減点はありませんが、多くの都道府県では運転中のイヤホン使用を条例で禁止しており、5万円以下の罰金や反則金が課されることもあります。
このように、イヤホン運転には厳しい罰則があるため、安全面を考えても控えることが大切です。
イヤホン装着で事故を起こした場合の過失割合の影響

イヤホン運転の怖さは「罰則」だけではありません。事故を起こした時の責任(過失割合)も重く見られる傾向があり、損害賠償請求で不利になる可能性が高くなります。
また、自転車での事故の例では、通常より5〜10%も過失が重く計算されるケースがあり、数百万円単位の賠償に発展することも。
さらに保険会社との示談交渉でも「イヤホンをしていた=注意義務違反」と扱われ、不利になる傾向があります。
イヤホン着用時の違反事例
ここでご紹介するのは自動車の例ではありませんが、イヤホンを着用したことによる事故の実例をご紹介します。
学生の自転車事故(千葉県)
2015年6月、千葉県でイヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転していた19歳の大学生が、横断歩道を渡っていた77歳の高齢女性をはねて死亡させた事故があります。この事故で、大学生は書類送検され、裁判では禁錮2年6月、執行猶予3年の有罪判決が出ました。
賠償責任としては、治療費、入院費、慰謝料、生きていれば得られた利益などを含め、約3,000万円から4,000万円規模の高額となった例です。
イヤホンでの運転による意識の低さが事故を招き、赤信号無視など過失も大きいと判断されました。
自転車のスピードは時速20〜30km程度でしたが、衝撃は甚大であり、民事的にも重い損害賠償責任が認められています。
データ参照元:内閣府(ホームページ)
上記のケースは、イヤホンを装着しながらの自転車運転が事故の主な原因であり、非常に危険であることがわかります。自動車と自転車では視界の範囲に違いがあるものの、どちらも『ながら運転』であることに変わりありません。
自動車の場合、音楽はスピーカーで聴くなどし、クラクションやサイレンなどの警告音を確実に聞き取れる状態にしておくことが大切です。
まとめ
イヤホンをつけて運転することは明確に道路交通法で禁止されているわけではありません。
しかし、周囲の音が遮断されて安全運転に支障をきたせば、安全運転義務違反として罰則や罰金、さらに過失割合の加重という大きなリスクにつながります。
- 「片耳なら大丈夫」は誤解
- 小音量でも注意力低下は避けられない
- 事故時は責任が重く、賠償金が高額化する
「少しくらいなら大丈夫」ではなく、運転中はイヤホンを外す習慣を心がけましょう。