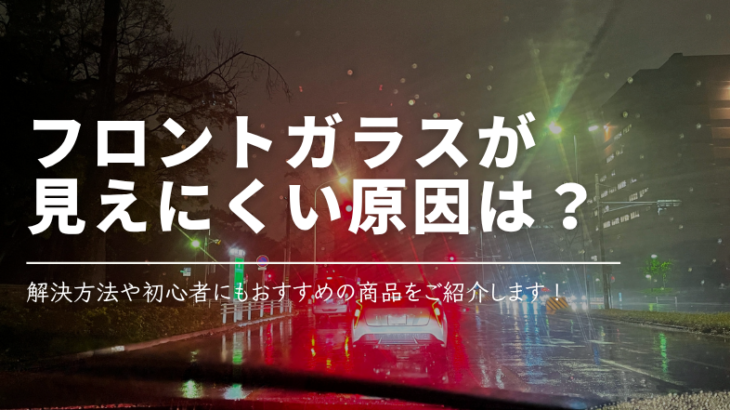こんにちは!アイカーマガジン編集部です!
現在の車は、ガソリンエンジン以外にもハイブリッドなどさまざまな動力源が使われています。
初めての量産型のハイブリッドカーは、1997年に登場したトヨタの「プリウス」であり、今ではガソリン車とハイブリッド車の違いを知っている人も多いでしょう。
しかし、2010年に量産型のEVカーである日産「リーフ」が登場し、さらにPHEVなど新しい技術も生まれたことで、それぞれの違いが分かりにくいと感じる人もいるかもしれません。
そこで本記事では、純粋なガソリンエンジン以外を動力源とする車について、それぞれの詳細を解説します。
\YouTubeではミニバンについて解説しています!よろしければご覧下さい/
「EV」とは電気を利用して走る車全般を指す言葉
EVは「Electric Vehicle」の略で、日本語では「電気自動車」という意味になります。
そのため、「EV」という言葉を聞くと、純粋な電気だけで走る車をイメージする人が多いかもしれません。日常会話でも、EVという場合はハイブリッドカーのようにエンジンを積んだ車を除いて話していることが多いです。
ただ、実際の意味としては「電気を使った動力源を採用している車」を指します。そのため、ハイブリッドカーのようにガソリンエンジンを搭載している車も広い意味ではEVに含まれます。
つまり、「EV」という大きなジャンルがあって、その中にハイブリッドカーなどが分類されているというわけです。
ただし、一般的には「電力だけで走る車」をEVと呼ぶことが多いです。そのため、それぞれのタイプの違いを表すときには、「EV」の前に特徴を示すアルファベットを付けて区別しています。
具体的には、以下の4種類です。
|
EV |
HEV(Hybrid Electric Vehicle) |
ハイブリッドカー |
|
BEV(Battery Electric Vehicle) |
バッテリー式電気自動車 |
|
|
PHEV(Plug in Hybrid Electric Vehicle) |
プラグインハイブリッドカー |
|
|
FCEV(Fuel Cell Electric Vehicle) |
燃料電池自動車 |
上記の名称は、それぞれの特徴を示す英単語の頭文字を組み合わせて作られています。
例えば、ハイブリッドカーの場合は「Hybrid」の頭文字「H」をEVの前につけて HEV と表します。
同じように、電気だけで走る車は「Battery」の「B」をつけて BEV、プラグインハイブリッドカーは「Plug-in」の「P」をつけて PHEV、燃料電池車は「Fuel Cell」の「F」をつけて FCEV と呼ばれています。
「ハイブリッドカー(HEV)」とは

|
システム |
方式 |
内容 |
代表的な車種 |
|
|
HEV |
ストロングハイブリッド |
シリーズ |
エンジンで発電し、モーターで走行 |
ホンダフィット、日産ノートなど |
|
スプリット |
エンジンとモーターで走行 |
トヨタプリウス、アクアなど |
||
|
マイルドハイブリッド |
パラレル |
エンジンが主体でモーターでサポート |
スズキスペーシア、ワゴンRなど |
ハイブリッドカー(HEV:Hybrid Electric Vehicle)は、いわゆる「ハイブリッドカー」のことです。1997年にトヨタが「プリウス」として初の量産型ハイブリッドカーを販売して以来、各メーカーからさまざまなハイブリッドカーが登場しています。
「ハイブリッド」という名前の通り、動力源はガソリンエンジン(ディーゼルエンジンを含む)とモーターの組み合わせで走行します。モーターを動かすためのバッテリーに必要な電力はガソリンエンジンから供給されるため、充電する必要はありません。
また、ハイブリッドカーには「ストロングハイブリッド」と「マイルドハイブリッド」の2種類があります。
ストロングハイブリッド
ストロングハイブリッドは、エンジンを使わず(エンジンを停止した状態で)モーターだけで走行できるタイプのことです。
その中でも、エンジンで発電した電力をバッテリーに蓄え、その電力でモーターを駆動させる仕組みを「シリーズ方式」と呼びます。代表的な車種にはホンダの「フィット」や日産の「ノート(e-POWER)」などがあります。
この方式ではエンジンは搭載されていますが、直接車を動かすのではなく、モーターに電力を供給するために使われます。この点では後述するBEVと似た走行形式ですが、ストロングハイブリッドはエンジンから電力を供給できるため、充電が不要な点が異なります。
また、エンジンとモーターの両方で車を動かすタイプは「スプリット方式」と呼ばれます。スプリット方式では、発進時や低速走行などトルクが必要な場面ではモーターを使用し、高速走行時にはエンジンを使用することで効率的な走行を実現しています。
代表的な車種にはトヨタのプリウス、アクア、ヤリスなどがあります。
マイルドハイブリッド
マイルドハイブリッドは、エンジンがメインで動力を担い、モーターが補助的な役割を果たす仕組みで、「パラレル方式」とも呼ばれます。この形式は軽自動車に多く採用されており、代表的な車種としてスズキの「スペーシア」や「ワゴンR」が挙げられます。
このシステムでは、発進時や加速時などエネルギーが必要な場面でモーターがエンジンをサポートすることで、燃費効率を向上させています。また、フルハイブリッドに比べてコストを抑えられる点もメリットです。
「バッテリー式電気自動車(BEV)」とは

バッテリー式電気自動車(BEV:Battery Electric Vehicle)は、ガソリンエンジンを搭載せず、電気の力だけでモーターを動かして走行する車のことです。
一般的に「EV」と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、このBEVタイプです。
代表的なメーカーには「テスラ」や「BYD」があり、日本国内では日産の「リーフ」やトヨタの「bZ4X」などが挙げられます。
ガソリンエンジンがないため、走行中に二酸化炭素を排出しないことから、環境に優しい車として近年世界的に普及が進んでいます。
ただし、現時点ではガソリン車やハイブリッドカーと比べて走行距離が短く、充電スポットが少ないという課題があります。一方で、1回の充電にかかる費用が少なく済むため、燃費(電費)が良いというメリットもあります。
「プラグインハイブリッド車(PHEV)」とは

プラグインハイブリッド(PHEV:Plug-in Hybrid Electric Vehicle)は、外部から電力を供給できるハイブリッドカーのことです。エンジンとモーターを搭載している点ではHEVと同じですが、外部電源を利用できるという違いがあります。
代表的な車種には、三菱自動車の「アウトランダーPHEV」や「エクリプスクロスPHEV」があります。バッテリー容量がHEVよりも大きいため、モーターだけでより長い距離を走行することが可能です。
また、電力が切れてしまった場合でもガソリンエンジンがあるため、走行を続けられる点はBEVに対する安心材料となります。
ただし、車種によってはBEVで一般的な「急速充電」に対応していない場合もあるため、モーター走行をメインに考えている方は注意が必要です。
「燃料電池自動車(FCEV)」とは

燃料電池自動車(FCEV:Fuel Cell Electric Vehicle)は、水素を燃料として走行する車です。
水素と空気中の酸素を化学反応させて発電する仕組みが特徴で、他のEVとは異なります。代表的な車種にはトヨタの「MIRAI」があります。
ガソリン車と同じような走行距離を実現し、燃料補充も数分で完了するため、ガソリン車と同じ感覚で使用できます。また、燃料電池システムの特性により、振動などの乗り心地も、他のEVと比べるとガソリン車に近いものとなっています。
他のEVではゼロから充電すると満タンになるまでに数時間かかるため、ガソリン車と同じ感覚で使用することができるのも魅力です。
ただし、車両価格はEVよりも高額であり、水素を補給する「水素ステーション」の数がまだ少ないため、実際に所有できる人は限られるでしょう。
日本の自動車メーカーが販売しているEVにはどのようなものがある?
上記でも各EVの代表的な車種を紹介しましたが、ここからはもう少し詳しく車種を紹介します。
HEV(ハイブリッドカー)は国内メーカーの各社から販売されていますので、ここではBEVとPHEVに絞ってリスト化しました。
BEV
BEVは、純粋に電気だけで走る車で、一般的に「EV」と呼ばれるものです。
| トヨタ | ・bZ4X |
| ホンダ | ・N-VAN e: ・Honda e(販売終了) |
| 日産 | ・サクラ ・リーフ ・アリア |
| マツダ | ・MX-30 EV MODEL |
| 三菱自動車 | ・eKクロス EV ・ミニキャブEV |
一般的なハイブリッドカー(HEV)と比べると取り扱いメーカーや車両が少ないですが、軽自動車から大型のSUVまで国内メーカーが取り揃えています。
PHEV
PHEVは、充電ができるハイブリッドカーです。
| トヨタ | ・RAV4 ・ハリアーZ ・プリウスG ・クラウンスポーツRS ・アルファード ・ヴェルファイア |
| レクサス | ・NX450h+ ・RX450h+ |
| マツダ | ・CX-60 PHEV |
| 三菱自動車 | ・アウトランダーPHEV ・エクリプスクロスPHEV |
BEVと比べると、販売しているメーカーは少ないです。
ただし、ガソリンエンジンを搭載しているため、電力確保に不安を感じる方には魅力的であり、今後車種が増えていく可能性があります。
FCEV
FCEVは、水素自動車です。
| トヨタ | ・MIRAI ・クラウンセダン |
水素ステーションの設置など、他のEVに比べて普及までの課題が多く、現在販売されている車種は限られています。
しかし、これらの課題が解決されれば、今後車種が増えていくと考えられます。
EV(BEV・PHEV)はどのくらい普及している?
EV全体で見ると、ガソリンをほとんど消費しない(使用しないものもある)ため、環境に優しい車両として世界中で普及が進んでいます。
ここからは、「BEV」と「PHEV」についてご紹介します。なお、ハイブリッドカー(HEV)については、世界的にも普及が進んでおり、新車販売のおおよそ33.2%となっています。
世界的な普及率
IEA(国際エネルギー機関)の調査によると、2023年の世界におけるEV(BEV・PHEV)の新車販売比率は約18%に達しました。特に2020年以降急速に普及が進み、2020年には4.2%だった普及率が2021年には9%、2022年には14%、そして2023年には18%と着実に増加しています。
EV普及率が最も高い国はノルウェーで、2023年には新車販売の93%がEVでした。次いでアイスランドが71%、スウェーデンが60%と続き、ヨーロッパ全体でも2023年には新車の5台に1台以上がEVとなっています。
販売台数で見ると、中国が世界のEV市場を牽引しており、2023年には世界のEV販売台数の約60%を占めました。ヨーロッパが25%、アメリカが10%を占めており、この3地域で世界のEV販売の95%を占めています。
国内の普及率
2023年の日本におけるEV普及率は3.6%で、主要国の中では低い水準です。アジアでは中国が38%、韓国が7.9%と続いています。
日本にはトヨタをはじめとする世界的な自動車メーカーが多く存在し、EV開発にも力を入れていますが、エネルギー事情や充電ステーションの整備の遅れが影響し、普及が進んでいない状況です。
EVの普及率は停滞気味となっているが、普及は続く
順調に普及してきたEVですが、ここ1~2年で勢いが停滞しています。ヨーロッパでは、政府による購入補助金の廃止やインフレ対策として金利が上昇したことにより、相対的に価格が高いEVの購入が難しくなったことが主な理由とされています。
実際、ドイツ最大の自動車メーカーであるフォルクスワーゲン(VW)は、EV戦略の見直しを発表しました。
日本でも充電ステーションの不足や、大雪時のバッテリー切れなどのリスクに加え、車両価格の高さが課題となり、普及が進みにくい状況です。
それでも、ガソリンエンジン車は徐々に減少していく見通しであり、EVの普及率は少しずつ上昇すると予測されています。
2020年には日本政府が「カーボンニュートラル宣言」を発表し、2035年までに新車販売を100%電動化する目標を掲げています(ただしHEVは引き続き販売可能)。また、アメリカのカリフォルニア州では2035年以降、HEVを含むガソリン車の新車販売を禁止する方針です。
このことから、日本を含む世界全体で今後EVの普及が進んでいくことは確実と言えるでしょう。
まとめ
現在では、ガソリン車に加え、ハイブリッドカーなど燃費が良く環境に優しい自動車が多く登場しています。これらを識別するために「HEV」「BEV」「PHEV」「FCEV」といった表記が使われています。
エコカーを検討している方は、それぞれの特徴や違いを理解することで、よりスムーズに車を選ぶことができるでしょう。今後、各EVは国内外でシェアを拡大し、対象となる車種も増えていくと予想されています。
本記事を参考に、ぜひ後悔のない車選びをしてください。